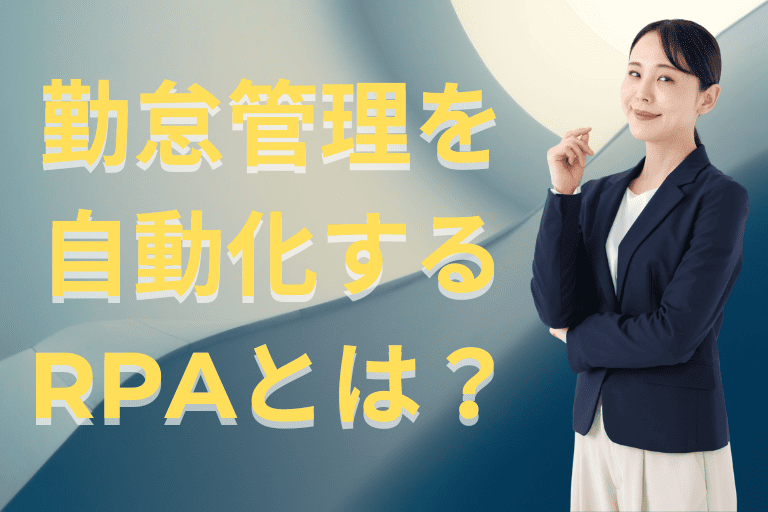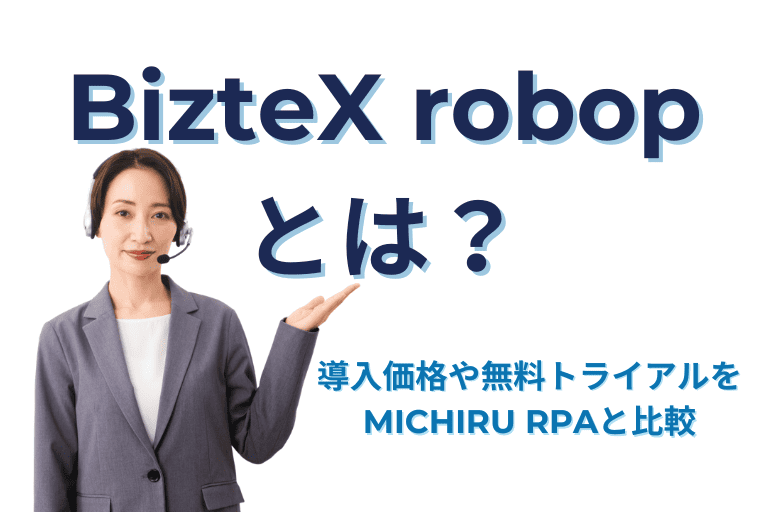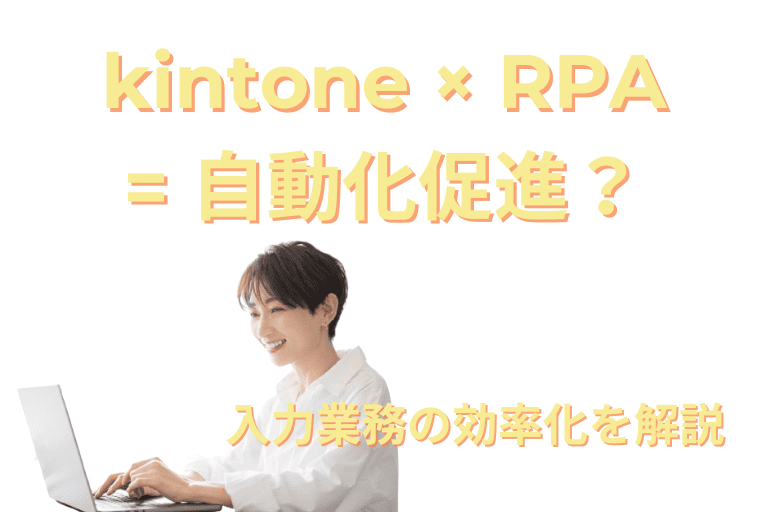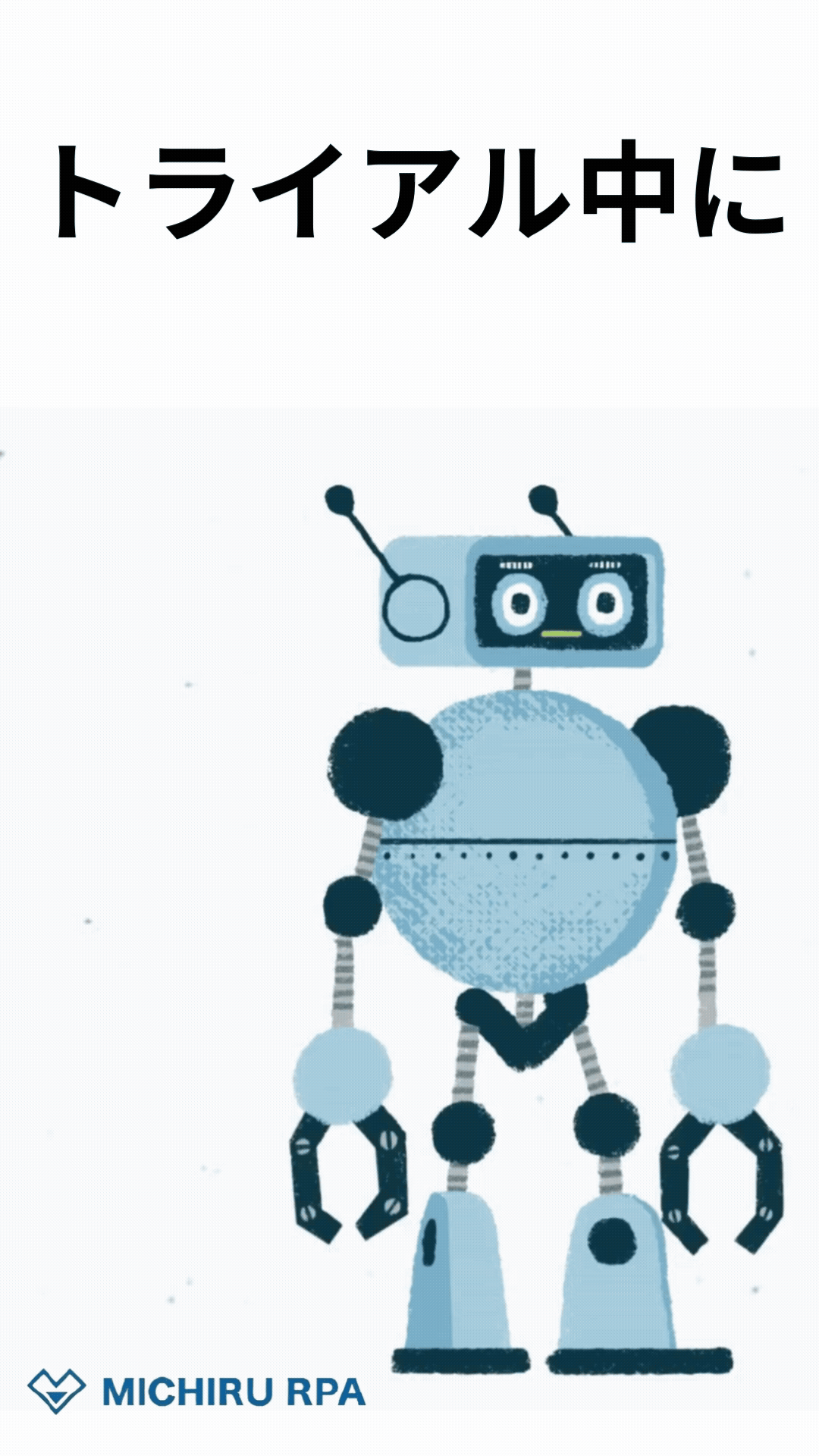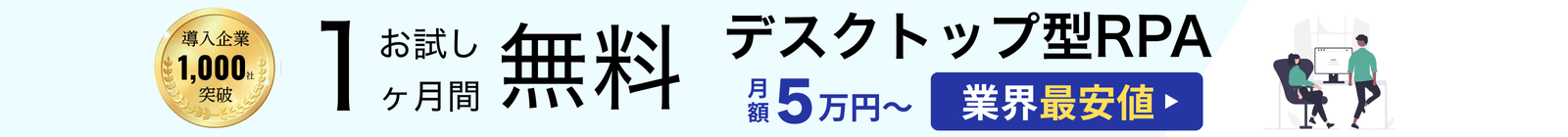RPAは、人がパソコン上で行なってる定型業務を自動化できるため、市場規模も年々拡大しており、導入する企業が増えています。
この記事では、RPAの社内展開を成功させる「ポイント」や「導入ステップ」について、詳しくご紹介していきます。
RPAの社内展開を検討する際は、ぜひ参考にしてみてください。
RPAの社内展開を成功させるポイントとは

RPAを円滑に社内展開するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
なぜなら、単にRPAツールを導入するだけでは、部分的な効率化のみで、効果を最大限に発揮できないからです。
ここからは、RPAの社内展開を成功させる「ポイント」について、詳しくご紹介していきます。
運用ルールを決める
RPAの社内展開を成功させるためには、明確な運用ルールの策定が必要です。
なぜなら、今までの業務であれば、各部署でルールを考えて、運用すればよかったのですが、RPAを各部署のルールで運用してしまうと、以下のような弊害が発生するからです。
- 不要なロボット開発による管理コストの増加
- 運用リスクが考慮されていないロボットの誤作動やトラブル
RPAを社内展開する際は、あらかじめルールを決めて、各部署が異なる方法で運用しないように注意し、全社的な効率化と一貫性を保つのがポイントです。
また、運用ルールを作成する際は、共通で使えるルールの他に「カテゴリー分け(開発・運用・管理)」をしておくことで、従業員が疑問を持った際にも迅速に解決できます。
マニュアルを作成する
RPAを運用する際は、ベンダーから提供されているマニュアルの他に、自社の環境に合わせた「独自マニュアル」の作成(ロボット開発手順やトラブル対応など)が有効的です。
なぜなら、RPAを社内展開する際は、さまざまな役割を担う従業員が、同じツールを使用することになるからです。
独自マニュアルの作成は、無秩序なロボット開発や運用を避け、効果的にRPAツールを利用するための「重要なガイドライン」になります。
- 基本的な操作方法
- ロボット開発ルール
- よくあるエラーメッセージとその解決策
- トラブル発生時の連絡先やサポート体制
- セキュリティルールやデータ管理に関するガイドライン
スモールスタートで運用していく
RPAを導入する際は、大規模なプロジェクトから開始するのではなく、スモールスタートで実績を重ねて、徐々に自動化を進めていくことがポイントです。
なぜなら、社内展開へのリスクを最小限にしておくと、効果的な作業範囲の拡大とともに、安定したRPAの導入を実現できるからです。
社内展開を進める際は、以下3つのプロセスでRPAを導入していくと円滑です。
- プロセス1:導入効果が得やすい部署(業務)から活用する
- プロセス2:成功事例を基に部署内での展開を拡大する
- プロセス3:他部署でも展開していく
ベンダーの導入サポートを活用する
RPAを円滑に社内展開するためには、ベンダーの専門的なサポートを活用するのも、大事なポイントです。
なぜなら、自分たちで社内展開してみると、今まで気づかなかった課題が発生し、社内のロボット開発者や、現場担当者だけでは解決できないこともあるからです。
ベンダーの導入サポートは、トラブルの解消だけではなく、運用方法のアドバイス(コツ)も教えてもらえるので、より導入効果を得やすくなります。
- 業務プロセスの分析と自動化対象の特定
- ツールのバージョンアップやメンテナンス
- FAQやナレッジベースの提供
- RPA推進・運用体制の構築支援
- ベストプラクティスの共有 など
また、ベンダーが開催している勉強会では、最新テクノロジーやトレンド、RPAの活用方法などを得られるので、積極的な参加をおすすめします。
- 日本語と英語に対応
- 月4回のリモートサポート
- メール / チャットサポート
- オンライン勉強会
RPAを社内展開した際の3大メリット

ここまでは、RPAを社内展開するための「ポイント」について、詳しくご紹介してきました。
ここからは、RPAを社内展開した際の「3大メリット」を解説していきます。
業務効率化の促進
RPAを社内展開する大きなメリットは、全社的な生産性の向上に繋がることです。
RPAは、特定の部署だけに導入しているケースでも、業務を効率化できますが、ある部署で成功した事例を別の部署にも横展開していくことにより、数少ない工数で生産性を向上できます。
運用体制が全社で統一
RPAの社内展開は、部門ごとに異なっていた運用プロセスを全社で標準化し、属人化していた業務を可視化できます。
運用体制の統一化は、各担当者が状況を把握しやすくなったり、システムの監視やメンテナンスを効率的に行えるメリットもあります。
人的ミスの削減
RPAは、決められた手順に基づいて、正確に業務を処理できるため、人的ミスが発生するリスクを大幅に削減することができます。
人が作業する場合は、疲れや慣れといったことが原因で、どんなにベテランな従業員でも、人的ミスを発生するリスクがあります。
しかし、RPAは、あらかじめ設定されたシナリオ通りに作業を進めるため、24時間365日いつ実行しても、データの正確性や一貫性が保たれ、不要なコストの削減や業務品質の向上を期待できます。
RPAを社内展開するための導入ステップ(流れ)

RPAを社内展開するための導入ステップは、一般的に以下となります。
ステップ1:自動化できる業務を選定
RPAを導入する際は、自動化できる業務の選定から始めます。
RPAは、繰り返し行う業務や、一定のルールに基づいて実行する業務に適しているため、自社の業務プロセスを確認し、自動化できる業務をピックアップします。
ステップ2:RPAの管理者を決める
次は、RPAを運用する上で、中心的な役割となる「RPAの管理者」を選出します。
管理者は、RPAを社内展開していく体制を整え、自動化の促進や教育、定期的な効果計測と検証を実施します。
管理者がいない場合は、RPAがスムーズに社内展開しない可能性もあるため、管理者の選出は非常に重要です。
ステップ3:ツールの選定
次に、RPAツールの選定を行います。
RPAの市場規模は、右肩上がり(2025年度:1,183億円見込み)なので、数あるツールの中から、自社に合ったツール選びが重要です。
ツールを選定する際は、使いやすさや機能性、拡張性、サポート支援体制などを考慮して、中長期的に使えるタイプがおすすめです。
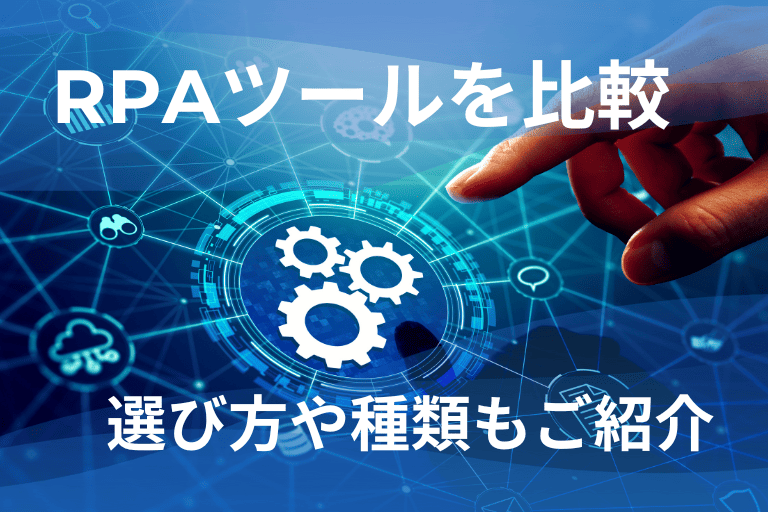
ステップ4:全社でツールをトライアル
次に、実際の使用感や、自社システムとの連携性などをテストしていきます。
トライアルは、導入後のミスマッチを防ぐためにも、非IT部門の従業員でも操作が可能であるか、シナリオ作成が容易かなど、いくつかのポイントを押さえながら、実施する必要があります。

ステップ5:RPAの本導入
トライアルで問題がなければ、全社展開を目指して、RPAを本格導入します。
RPAを本導入する際は、全社展開する前に、個人や部門単位といった「小規模な範囲」から自動化を始め、導入課題や効果などを実証し、規模を拡大していくのがおすすめです。
スモールスタートは、自動化のノウハウや知見を溜めながら、社内展開できるので、円滑かつ効果的に導入をすることが可能です。
まとめ

本記事では、RPAの社内展開を成功させるためのポイントと、導入ステップについて解説しました。
RPAの社内展開は、全社的な生産性の向上や、人的ミスの削減に繋がったりと、さまざまなメリットがあります。
今後、RPAを社内展開される際は、導入ステップなどを参考にしながら、ツール選定してみてはいかがでしょうか?
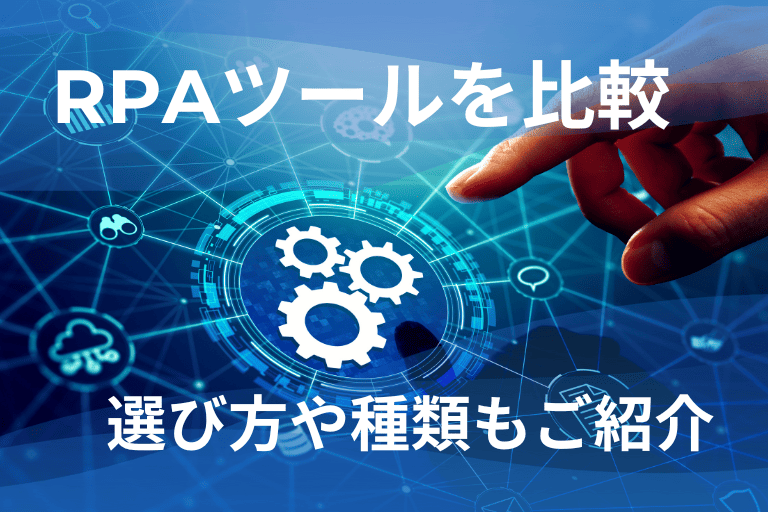
月額50,000円で利用できるデスクトップ型のMICHIRU RPA
- 日本語と英語に対応
- 月単位での契約更新
- 1ヶ月の無料トライアル有
- メール・チャットサポートは無料