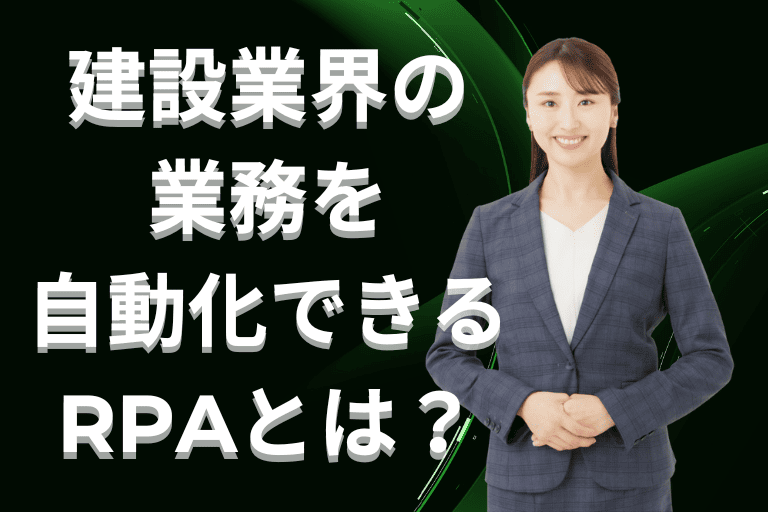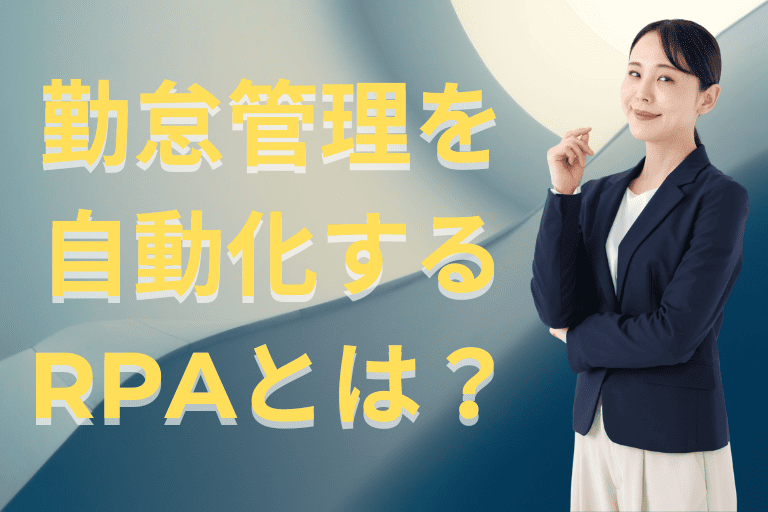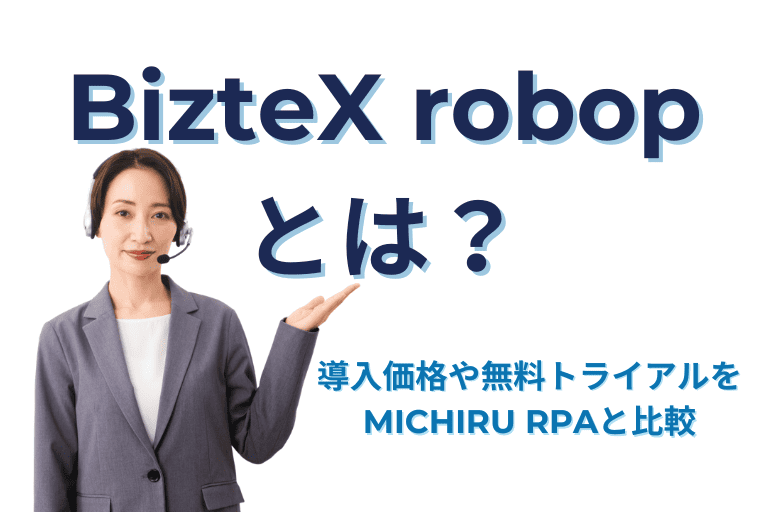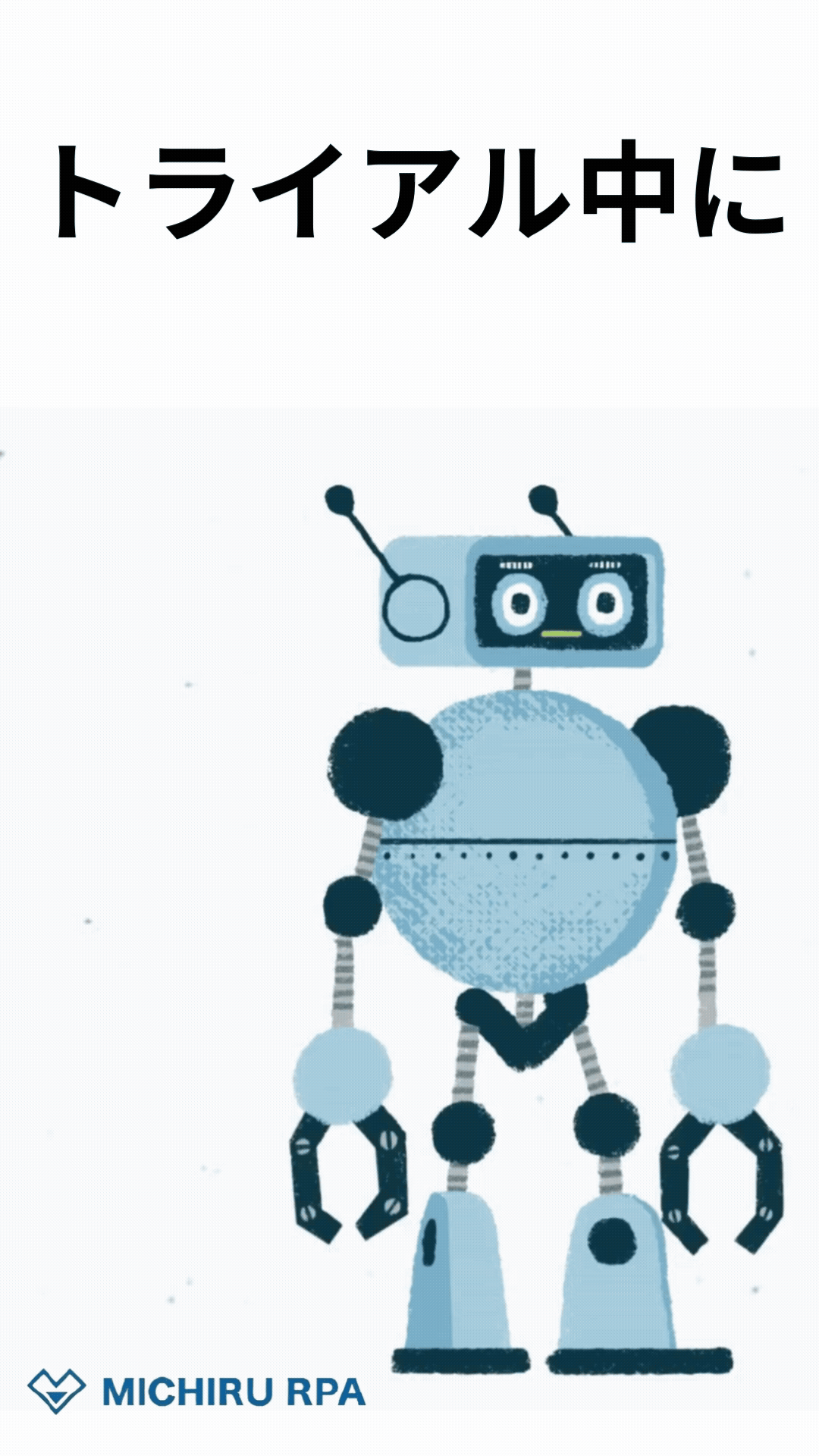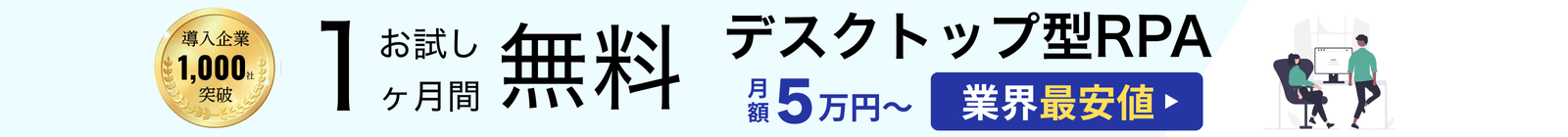近年、多くの企業では、業務の効率化や生産性の向上を目的に、自動化ツールの導入を進めています。
特に、定型(ルーティン)業務は、RPAが得意とする領域であり、作業時間の大幅な短縮や、人的ミスの削減など、作業担当者の負担を大幅に軽減します。
本記事では、RPAで効率化できる具体的な定型(ルーティン)業務や、RPAツールの選定ポイントを詳しく解説していきます。
定型業務を効率化できるRPAとは

定型業務を効率化できるRPAとは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略で、人が手作業で行っている反復(ルーティン)業務やデータ処理を、ソフトウェアロボットが自動で代行する技術です。
RPAは、企業や組織のさまざまな業務プロセスを自動化し、作業の正確性やスピードを向上させるツールなので、近年多くの企業で導入が進んでいます。
具体的には、データ入力・請求書処理・受発注管理・帳票作成・システム間のデータ連携などで、膨大な時間と労力を必要とする反復(ルーティン)業務を、ミスなく迅速に実行できる点が特徴です。
従業員は、RPAの導入により、付加価値の高い業務や、クリエイティブな仕事に集中できる環境が整うため、企業全体の効率化と生産性の向上に繋がります。

RPAで効率化できる定型業務

ここまでは、業務の効率化を実現するRPAについて、詳しくご紹介してきました。
RPAで効率化できる定型業務は、作業ルールや手順が明確で、繰り返し発生しているパソコン業務です。
ここからは、RPAで効率化できる定型業務を解説していきます。
効率化1:入金消込
入金消込は、企業が日々行う経理業務の中でも、時間と労力がかかる定型業務のひとつです。
具体的には、銀行口座に振り込まれた入金情報と、請求書や売掛金データを照合して、入金を確認・記録する作業となります。
この業務は、企業の資金管理や、会計処理の正確性を保つために欠かせませんが、取引件数が多かったり、複数の銀行口座を管理していると、照合作業に時間がかるため、人的ミスが発生しやすくなります。
そこで、企業側は、RPAを活用することで、入金データの取得から、システムへの入力・消込結果の確認・レポート作成までを自動化することが可能です。
RPAは、24時間稼働できるため、営業時間外でも作業を行えるので、入金消込を効率化しながら、処理の遅延や人的ミスのリスクも軽減できます。
効率化2:競合他社の情報収集
競合他社の情報収集は、自社の市場での立ち位置を把握し、戦略的な意思決定を行うために、必要不可欠な業務です。
具体的には、競合企業のウェブサイト・ニュースリリース・SNS・価格情報・製品・サービス動向などを継続的に調査・分析し、自社のマーケティングと商品開発(営業戦略)に役立てることを目的としています。
しかし、この業務は、日々膨大な量をチェックする必要があるので、情報の抽出と整理に手間がかかるうえ、抜け漏れや更新の遅れが発生しやすいです。
そこで、注目されているのが、競合他社の情報収集を効率化できるRPAの導入です。
RPAは、ウェブサイトの定期巡回・特定キーワードを含む記事の収集・価格の変動チェック・情報のスプレッドシートへの自動記録など、一連の作業を正確かつ、迅速に実行することが可能です。
現場担当者は、RPAの導入により、リアルタイムに近い情報収集が可能となり、市場での優位性を確保することができます。
効率化3:顧客情報のリストアップ
顧客情報のリストアップは、営業活動やマーケティング施策を効果化するために、企業がターゲットとなる顧客の情報を収集・整理して、リストを管理する業務です。
この作業は、顧客名・連絡先・業種・所在地・過去の取引履歴など、多岐にわたるデータを正確にまとめる必要があり、取引先が多い企業では膨大な時間と労力がかかります。
また、複数の情報ソースからデータを収集・統合する際は、入力ミス・情報の重複・抜け漏れといった人的ミスが発生しやすく、データの精度に課題が生じます。
そこで、注目されているのが、顧客情報のリストアップを効率化できるRPAの活用です。
RPAは、ウェブサイト・既存の顧客データベース・外部サービスなどから、必要な情報を自動で収集・抽出できるため、あらかじめ設定されたフォーマットでリスト化できます。
また、RPAは、顧客リストの更新作業も自動化できるため、最新かつ正確な情報を取得することが可能です。
効率化4:経費精算
経費精算は、従業員が業務上発生した交通費・出張費・接待費などの立替経費を会社に申請し、承認や支払いを受けるための手続きです。
この作業は、企業規模を問わず、日常的に発生するものであり、申請内容の確認・領収書の照合・システムへの入力・承認フローの管理・仕訳処理など、多くの手間と時間を要するルーティン業務です。
また、これらは、申請ミス・入力漏れ・不正申請のチェックなど、人の目による確認作業が必要になるため、処理の正確性やスピードに課題を抱える企業も少なくありません。
そこで、注目されているのが、経費精算を効率化できるRPAの導入です。
RPAは、経費申請データの取り込みから、領収書のチェック・承認ステータスの管理・仕訳情報の自動登録までを自動化することが可能です。
これにより、現場担当者は、作業時間の短縮と、人的ミスを削減できるため、業務負担を大幅に軽減できます。
効率化5:メール送信(対応)
メール送信(対応)は、顧客・取引先・社内の関係者とのやり取りを、円滑に行うために欠かせないコミュニケーションのひとつです。
しかし、メール業務は、手作業で行うと膨大な時間がかかるうえ、入力ミスや、送信漏れといった人的ミスが発生しやすいという課題があります。
そこで、注目されているのが、メール送信(対応)を効率化するRPAの活用です。
RPAは、あらかじめ設定した条件に基づいて、特定の宛先に自動でメールを送信したり、受信したメール内容を解析して、適切な返信文を生成・送信したりすることが可能です。
これにより、現場担当者は、業務時間の短縮や、対応の正確性が向上し、付加価値の高い業務に集中することができます。
また、RPAは、定時送信・定型文の自動挿入・ファイルの自動添付などにも対応できるため、ルーティンワークの効率化に大きく貢献します。
効率化6:販売状況の分析
販売状況の分析は、自社製品やサービスが「どのくらい売れているのか」を把握し、売上の傾向・課題・今後の販売戦略を立てるために欠かせない業務です。
一連の作業(販売データの収集・整理・集計・グラフ化・レポート作成)は、毎日 / 週単位 / 月単位で継続的に行う必要があり、手作業では多くの時間と労力を要します。
特に、複数の店舗・ECサイト・販売チャネルを運営している企業は、膨大なデータを正確に処理することが求められ、ミスや処理の遅れが意思決定に影響を及ぼします。
そこで、注目されているのが、販売状況の分析を効率化するRPAの導入です。
RPAは、売上データの取得・各種フォーマットへの転記・ExcelやBIツールを活用した集計・分析・レポート作成までのプロセスを、ルールに従って正確かつ迅速に実行できます。
これにより、企業側は、業務負担の軽減と分析結果の精度が向上するため、経営陣が意思決定を早く行えるようになります。
効率化7:受注・在庫管理
受注・在庫管理は、商品やサービスをスムーズに提供するために不可欠な業務であり、在庫状況をリアルタイムで把握・更新しながら、必要に応じて発注・出荷を行います。
この業務は、販売管理システムや、在庫管理システムなどの複数ツールを使いながら、大量のデータを処理する必要があり、手作業ではミスや遅延のリスクが高まります。
特に、注文数が多い企業や複数拠点で在庫管理を行う場合は、業務が複雑になるため、現場担当者に大きな負担がかかります。
そこで、注目されているのが、受注・在庫管理を効率化するRPAの活用です。
RPAは、注文情報の自動取り込み・在庫数の照合・更新・欠品時のアラート発信・出荷指示の作成・各種帳票の出力までを、定められたルールに基づいて、正確かつ高速に実行することが可能です。
これにより、企業側は、人的ミスの防止をはじめ、業務時間の短縮と迅速な顧客対応を実現し、企業の信頼性と共に、業務の効率化を大幅に向上させます。
効率化8:見積書・請求書の作成
見積書・請求書の作成は、営業活動や取引業務において、日常的に発生するルーティン業務であり、取引先との信頼関係を築くうえで、非常に重要です。
企業は、取引が行われるたびに、商品やサービスの内容・金額・納期・支払条件などを記載した書類を作成し、迅速に送付する必要があります。
しかし、これらの業務は、手作業で行うと、情報の転記ミス・作成漏れ・フォーマットの不統一などが発生しやすく、作成から送付までに時間がかかるという課題もあります。
そこで、注目されているのが、見積書・請求書の作成を効率化するRPAの導入です。
RPAは、受注情報や顧客データをもとに、あらかじめ定められたテンプレートに、必要な情報を自動で入力し、見積書や請求書をミスなく迅速に作成・保存・送付することが可能です。
さらに、RPAは、社内の会計システムやCRMと連携させることで、作業負担を省けるため、業務の正確性と効率化が飛躍的に向上します。
効率化9:勤怠管理
勤怠管理は、従業員の出勤・退勤時間・休憩時間・残業・休日出勤・休暇取得などの勤務状況を、正確に記録・管理する業務であり、人事と労務部門にとって欠かせない定型業務です。
勤怠データは、法令遵守をはじめとし、給与計算の正確性と労働時間の適正管理を実現するためにも、正確な処理が求められます。
しかし、手作業での勤怠管理は、システム入力・異常値のチェック・月次レポートの作成に多くの時間と労力がかかり、人的ミスや対応の遅れが発生します。
そこで、注目されているのが、勤怠管理を効率化するRPAの活用です。
RPAは、勤怠管理システムからのデータ抽出・エラーチェック・データ修正・月次集計・CSV出力・レポート作成など、一連のプロセスを自動化できるため、煩雑な業務を大幅に削減できます。
さらに、RPAは、大量のデータ処理を得意としているので、処理スピードの向上と業務品質の安定化が実現します。
また、勤怠管理の正確性は、従業員からの信頼を得られるため、企業としてのコンプライアンス強化にも繋がります。
効率化10:日報・レポートの作成
日報・レポートの作成は、業務の進捗状況・成果・課題・データ分析の結果などを、関係者に共有するため、定期的に作成される報告資料であり、企業のあらゆる部門で必要な作業です。
これらの業務は、一見単純に見えても、情報の収集・集計・入力・レイアウト調整といった細かな工程が必要で、手作業では時間がかかるうえに、ミスが発生しやすいという課題があります。
そこで、注目されているのが、日報・レポートの作成を効率化するRPAの活用です。
RPAは、システムやスプレッドシートから必要なデータを抽出し、定められたフォーマットに自動入力できるため、レポート作成のプロセスを無人で実行することができます。
これにより、日報・レポートは、作成のタイミングや内容に一貫性が保たれるため、管理・分析の質が向上します。
RPAで効率化できない業務

ここまでは、RPAで効率化できる定型業務について、詳しくご紹介してきました。
RPAは、手順が毎回異なる非定型業務や、判断基準が曖昧で、ルール化できない業務を自動化することができません。
ここからは、RPAで効率化できない業務を解説していきます。
非定型業務
非定型業務は、手順や判断基準が明確に定まっておらず、状況に応じて柔軟な対応や、人間の判断を必要とする業務のことを指します。
例えば、クリエイティブなコンテンツ制作などは、その都度、判断や創造性が求められるため、RPAでの自動化には不向きです。
また、非定型業務では、コミュニケーション力・感情への配慮・過去の経験や知識が必要になる場面も多く、AIやRPAで完全に代替できません。
そのため、非定型業務においては、RPAに頼るのではなく、人間のスキルや判断を活かしながら、従事する必要があります。
- クライアントとの折衝
- トラブル対応
- マーケティング戦略の立案
- 新規事業の企画
- クリエイティブなコンテンツの制作
人の判断が必要な業務
人の判断が必要な業務は、定められたルールや手順では対応できず、その都度、状況や背景を踏まえて、柔軟に意思決定を行う業務のことを指します。
例えば、クレーム対応では、業務知識だけでなく、経験・直感・倫理観・感情的な洞察力など、人間ならではの判断能力が求められるため、RPAによる自動化は現実的に困難です。
また、人の判断が必要な業務では、予測不能な変化や、複雑な思考を必要とすることが多く、RPAに任せるとリスクを伴います。
そのため、RPAの導入を検討する際は、すべての業務を自動化するのではなく、人の判断が必要な業務と、ルーティンワークを明確に切り分けることが大切です。
- クレーム対応
- 採用面接
- 経営判断
- 商談での価格交渉
- クリエイティブな企画立案
- 顧客の感情に配慮したコミュニケーション
パソコン以外での業務
パソコン以外での業務は、現場作業や人の手を使って行う実務的な作業など、デジタル環境に依存しない業務全般を指します。
例えば、フィールド営業での訪問活動は、物理的な行動や、対人対応を含むため、RPAでの自動化は不可能です。
なぜなら、RPAは、パソコン上の定型業務を対象としたソフトウェアロボットであり、パソコンを介さない作業は対象外だからです。
もちろん、RPAは、IoT・ロボティクス・AIカメラなど、他の技術と組み合わせることにより、一部作業を効率化することは可能ですが、単体での自動化には限界があります。
そのため、RPAを導入する際は、自社の業務の中で「パソコン上で完結する定型業務」と「現場での物理的作業」を明確に分類し、適した効率化を選定することが重要です。
- 製造現場での機械操作 / 製品の組み立て
- 倉庫での棚卸し / ピッキング
- フィールド営業での訪問活動
RPAで業務を効率化する際のメリット

ここまでは、RPAで効率化できない業務について、詳しくご紹介してきました。
RPAは、スピードと正確性が求められる現代ビジネスにおいて、単なる自動化ツールではなく、企業の競争力を高める重要な施策です。
ここからは、RPAで業務を効率化する際のメリットを解説していきます。
メリット1:定型業務の自動化
RPAは、24時間365日ミスなく、ソフトウェアロボットが稼働するため、業務効率の最大化を図れます。
定型業務の自動化は、作業スピードが大幅に向上するだけではなく、人的ミスを防止できるので、本来集中すべきコア業務や、創造的な業務に注力することが可能です。
また、RPAは、繁忙期や人手不足の状況下においても、柔軟な対応ができるため、業務負荷の偏りを防ぎ、組織全体の生産性を向上します。
さらに、定型業務の自動化は、業務の標準化が進むため、業務プロセスを可視化するなど、副次的なメリットも期待できます。
メリット2:人的ミス・コストの削減
RPAは、業務作業でのミスを減らし、無駄な工数や人件費などを抑えることで、業務全体の効率化と生産性を高めます。
ルーティンワークの多くは、人手による繰り返し作業が中心であり、確認不足・入力ミス・処理漏れなど、人的ミスが発生するリスクを常に抱えています。
人的ミスは、顧客対応の遅れ・取引先との信頼関係悪化・二重チェックの強化など、新たな負担を生み、結果としてコストの増加を招く原因となります。
しかし、RPAは、決められたルールに基づいて、正確に作業を繰り返すため、人的ミスの発生をゼロに近づけることが可能です。
さらに、RPAは、短時間に大量処理もできるので、残業時間や人員配置の最適化に繋がり、人件費や運用コスト削減のメリットがあります。
メリット3:顧客満足度の向上
RPAは、問い合わせ対応の迅速化・正確な情報提供・ミスのない処理など、顧客に対して一貫性のある高品質なサービスを提供します。
例えば、RPAは、見積書や請求書の即時発行・受注確認メールの自動送信・サポート対応履歴などを効率化できるので、顧客を待たせることなく、必要な情報やサービスを提供できます。
また、RPAによる業務の効率化は、従業員が顧客対応や提案活動など、人間にしか対応できない業務に集中できるため、より丁寧で柔軟なサービスが行えます。
さらに、RPAは、ミスの削減や業務の標準化によって、顧客対応の品質にばらつきがなくなり、業務品質を安定化できるメリットもあります。
メリット4:生産性の向上
RPAは、人手で行っていた業務を、高速かつ正確に処理できるため、煩雑な事務作業に時間を取られることなく、付加価値の高い業務に時間を割けます。
また、RPAは、24時間365日稼働できるので、業務処理のスピードが飛躍的に向上し、処理待ちの時間や、残業時間の削減にも繋がります。
さらに、RPAによる効率化は、業務の属人化を解消し、組織全体の生産性を高められるメリットもあります。
メリット5:人手不足の解消
RPAは、限られた人員で、より多くの業務をこなすことが可能なので、慢性的な人手不足の解消に繋がります。
特に、業務量の波が激しい部署においては、RPAが即戦力として機能し、人員補充の代替策としても有効的です。
RPAで業務を効率化した事例

RPAは、人間よりも業務の進め方が効率的なので、ルーティンワークを改善することができます。
以下は、RPAで業務を効率化した具体的な事例です。
| 企業 / 部門 | 業務内容 | 導入効果 | 具体的な数値 |
|---|---|---|---|
| 製造業 経理部門 |
請求書の発行 | 作業時間の短縮 | 1件あたり10分→2分 作業時間80%削減 |
| 小売業 人事部門 |
勤怠データの集計と入力 | 入力ミスの削減 締め作業の迅速化 |
月20時間→月5時間 作業工数75%削減 |
| 保険会社 営業部門 |
顧客情報のリストアップ | 業務の効率化 | 月40時間→月8時間 作業時間80%削減 |
| IT企業 マーケティング部門 |
競合他社の情報収集 | データ抽出の自動化 分析時間を確保 |
週5時間→週30分 作業時間90%削減 |
| 建設会社 総務部門 |
経費精算データの照合 | 処理スピードの向上 確認業務の削減 |
月100件→月200件 生産性2倍 |
| 通信業 カスタマーサポート部門 |
問い合わせ対応の履歴入力 | 対応品質の向上 | 対応時間5分短縮 1日あたり20%削減 |
| 医療機関 管理部門 |
在庫管理と発注処理 | 人的作業の軽減とミスの防止 | 人的ミス3%→0% |
| 教育機関 教務部門 |
出席データの収集と集計 | 業務負担の軽減 | 月15時間→月2時間 作業時間約87%削減 |
| 金融機関 事務センター |
口座振替の入金消込 | 作業の削減と確認精度の向上 | 月30時間→月5時間 工数83%削減 |
| 運輸会社 営業事務部門 |
見積書の作成業務 | 作成時間の短縮 対応スピードの改善 |
1件15分→3分 作業時間80%削減 |
RPAツールを選ぶポイント

ここまでは、RPAで業務を効率化した事例について、詳しくご紹介してきました。
近年、RPAは、業務の効率化・人手不足への対応・働き方改革の一環として、さまざまな企業で導入されていますが、ツールごとに機能や運用体制が異なります。
ここからは、RPAツールを選ぶポイントを解説していきます。
ポイント1:サポート体制
サポート体制とは、RPAツールを導入・運用するうえで、ベンダーや提供会社がユーザーに対して提供するRPAの支援(教育コンテンツなど)や、トラブル対応全般を指します。
RPAツールは、導入後すぐに効果が出るものではなく、業務に合わせたロボットの設計・実装・メンテナンス・継続的な改善と運用が必要です。
特に、RPAをはじめて導入する企業にとっては、業務の効率化を進めるにあたり、操作に関する疑問・トラブル対応・導入支援・操作トレーニング・定着までのフォローアップが成功の鍵となります。
また、RPAツール選定時は、操作マニュアル・FAQの充実度・チャットや電話での対応有無・日本語でのサポート有無・専任担当者の有無なども、確認すべきポイントです。
ポイント2:無料トライアルの有無
無料トライアルの有無とは、RPAツールを本格導入する前に、一定期間・一部機能を無料で試用できるかについてで、RPAツールを選ぶ際に重要なポイントです。
近年、RPAは、業務効率化のために、多くの企業で活用されていますが、ツールによって機能性・操作性・導入コスト・サポート体制が異なるため、いきなり本契約を結ぶことは危険です。
無料トライアルを提供するRPAツールであれば、自社の業務に適しているのかを、実際に操作しながら確認できるので、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
特に、RPAツールは、使ってみなければわからないポイントも多く、導入後の運用・拡張も視野に入れて選ぶ必要があります。
- 操作が直感的であるか
- 業務との連携がスムーズか
- 社内のITスキルレベルで扱えるか
- サポート体制は充実しているか

ポイント3:ツールの機能性と拡張性
ツールの機能性と拡張性とは、RPAツールが備えている機能の充実度と、将来的な業務拡大や他システムとの連携に対応できる能力を指し、RPAツールを選ぶ際の重要なポイントです。
RPAの導入にあたっては、単に一部の業務を自動化するだけでなく、企業全体の業務効率化や、DX推進を見据えた長期的な活用が求められます。
そのため、RPAツールを選定する際は、ツールの機能性と拡張性(カスタマイズや他システムとの連携)を把握しておくことが大切です。
ポイント4:既存システムとの相性
既存システムとの相性とは、RPAツールが自社で運用している業務システムやアプリケーションと、スムーズに連携・動作できるかを示す重要な選定ポイントです。
RPAツールは、業務の自動化を実現するうえで、Excel・ERP・会計ソフト・CRM・メールソフト・クラウドサービスなど、さまざまなシステムやツールと連携して動作するため、既存環境との適合性が導入効果を左右します。
システムの仕様によっては、思ったようにロボットが動作しなかったり、予期せぬエラーが発生したりするケースも少なくありません。
そのため、導入前には、RPAツールが自社の基幹システムや業務アプリと、問題なく連携できるのか、実際の操作環境で動作検証を行うことが大切です。
まとめ

本記事では、RPAで効率化できる具体的な定型(ルーティン)業務や、RPAツールの選定ポイントについて、詳しく解説してきました。
定型(ルーティン)業務は、RPAが得意とする領域であり、作業時間の大幅な短縮や、人的ミスの削減など、作業の効率化を後押しします。
業務の効率化に悩んでいる企業は、本記事を参考にしながら、RPAツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか?
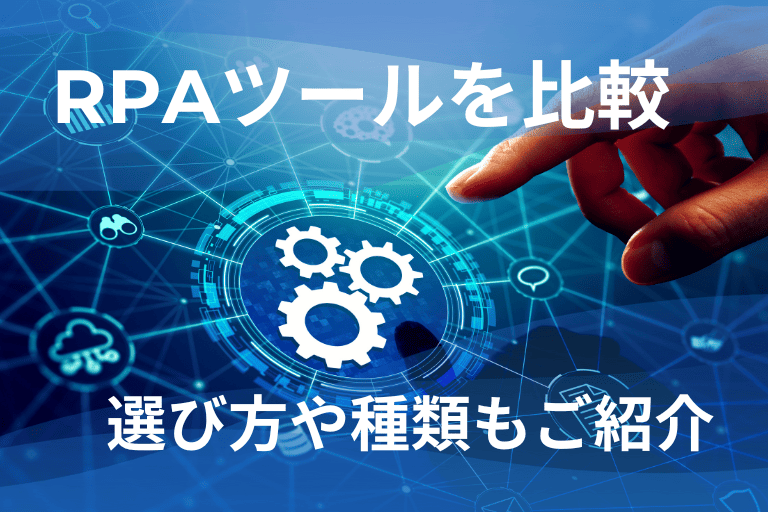
MICHIRU RPAのトライアル
- リモートサポート付
- 1ヶ月間無料
- トライアルから本導入まで完全サポート
- 日本語と英語に対応
- 1ライセンスで同時編集5台 / 同時実行1台の権限を付与