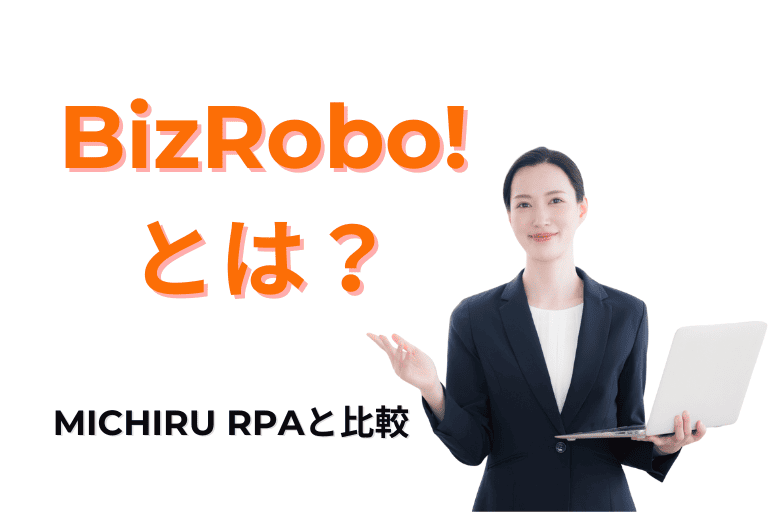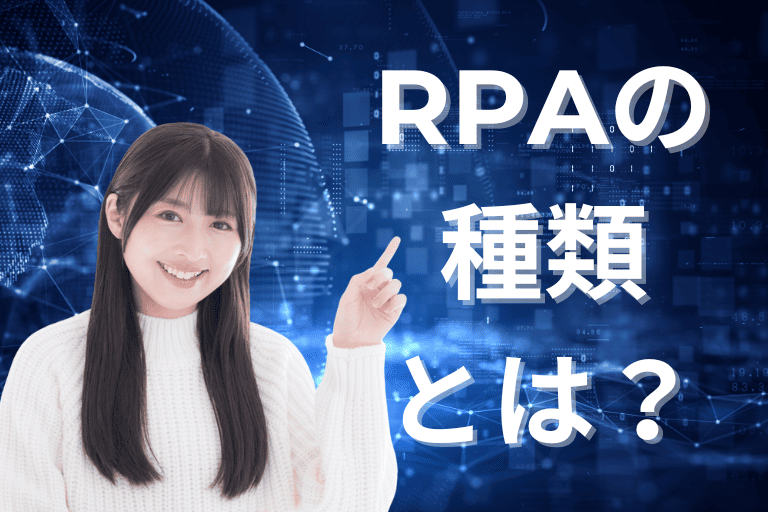RPA=Robotic Process Automationは、オフィスのパソコン操作を自動化する、いわば「オフィスのロボット」を意味します。
RPAは、働き方改革・DX推進の加速にともなって、多くの企業や自治体で急速に導入が進んでいるツールです。
労働時間の削減、業務の効率化、生産性の向上、人材不足の解消など、多くの課題を解決するツールとして「RPA」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、RPAツールの導入を検討しようと思っても、RPAを体系的に学習する機会が少ないのが実情です。
そこで、RPAの導入を検討している方や興味がある方に向けて、RPAツールと関連用語の意味と違いについて解説していきます。
略語も多く意味がわかりにくい、用語の意味を覚えるのは大変、という方にも、RPAに関する正しい知識を基礎から学ぶ一助になれば幸いです。
そもそもRPAとは?

RPA(Robotics Process Automation)は、いわば「オフィスのロボット」です。
オフィスのPC業務の手順を人間がRPAに教えると、その通りに自動で仕事を繰り返し行ってくれます。
そのため、ルーチンワークと言われるような定型・定期業務を劇的に効率化するツールとして注目されています。
また、RPAツールの操作に、プログラミングの知識は必要ありません。
RPAで自動化する一連の操作の流れを「シナリオ」や「ワークフロー」と呼びますが、それらはプログラミングのスキルがなくても作ることができるため、導入のハードルが低いことも人気の理由です。
なぜ今、RPAが話題になっているのか?

近年、RPAの導入が拡大したことで、運用の成功事例が紹介される機会が増えてきました。
その効果に多くの人が注目し、話題になっています。
特に、先行して急速にRPA導入が進んでいた金融業界からは、多くの成功事例が報告され話題になりました。
たとえば、数千人分にも相当する業務量の削減に成功した事例や、創出した時間と人員で、営業部門や海外事業の強化を実現した事例など、大きなインパクトを与えた実例がいくつもあります。
RDAとの違いは?
RPAとよく似た言葉に、RDAがあります。RDAはRobotic Desktop Automationの略です。
RDAは、PCにインストールして使うことに限定したRPAの一種です。
それ以外の機能や、意味はRPAとほぼ同じと考えてよいでしょう。
デジタルレイバーのいる場所の違い
デジタルテクノロジーが人に代わって業務を担うことや、その労働力を「デジタルレイバー」(仮想知的労働者)といいます。
また「デジタルレイバー」はRPAやRDAのような業務を自動化するソフトウエアロボットを指して使われることもあります。
RPAはサーバ・PC・クラウドなどにインストールしますが、RDAはPCにインストールし、基本的にはスタンドアロン、あるいは数台のみをネットワークでつないで動作させます。
つまり、RPAとRDAの機能・意味は同じだが、デジタルレイバーのいる場所が異なるソフトウェアということです。
ロボットの意味は?FAやROBOTICSとの違いは?

一般的にイメージされる、いわゆるロボット(FA=Factory Automation)は、オフィスのロボットであるRPAとは利用シーンが異なります。
FAは、アームやコンベアなどのハードウェアを工場業務で動かすのに対し、RPAはオフィスのソフトウェアシステムで行う業務限定で機能します。
つまり、FAは車などの工場にあるロボット、RPAはオフィス業務のためのロボットであり、使われる業務・場面と、動かす対象がハードウェアなのか、パソコン上のソフトウェアなのかに違いがあります。
FAとRPAに共通する本質は、ロボットが自動で繰り返し動くようにプログラミングし、これをコントロールする装置とソフトウェアがあること、また、これらの組み合わせにより自動で動くということです。
「ロボティクス」とは、この本質に当たる技術、またはこうした技術に関する学問を意味します。
AIとの違いは?自動化の仕組みの比較
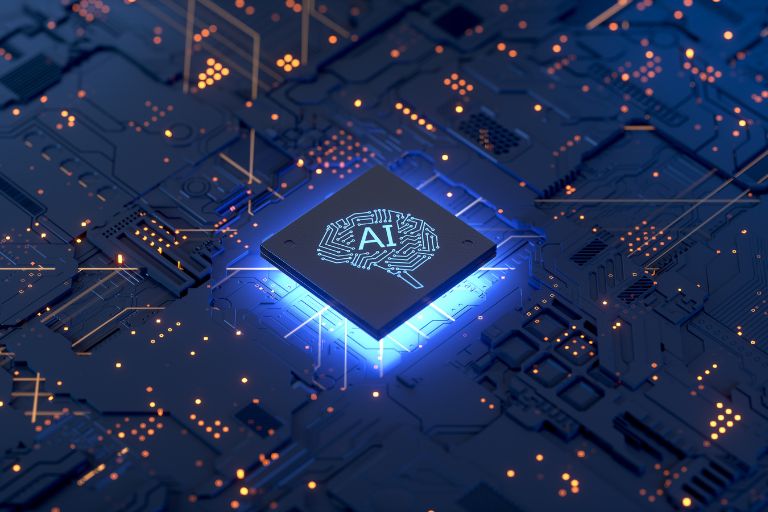
AIとRPAは、作業を自動化して人の手だけに依存しない業務体制をつくることができる点で似ていますが、その意味は異なります。
AIは、最近では機械学習を指して使われることが多くなってきました。
機械学習とは、AIが与えられたデータを分析して特徴や規則性を見つけだし、それらを目的のための判断や予測に生かすことができる技術です。
一方、RPAはデータから学習することはありません。
人間が設定した通りの操作を自動化、反復する仕組みをもっています。つまり、反復する単純作業向きなのです。
このAIとRPAを組み合わせることによって、あたかも人間のように意味を理解して判断しているような高度な知能を持ち、反復作業を行うことができるようになります。
実際に、AIとRPAを組み合わせたソリューションを業務に活かす場面が増えてきました。
AIとRPAの組み合わせは高度な自動化を実現

RPAは、AIチャットボットなどのAIと合わせて導入することにより、更に高度な業務自動化を実現できます。
例えば、文字認識精度やレイアウト解析精度の高いAI-OCR(Optical Character Recognition)とRPAを組み合わせて導入する方法があります。
この場合、紙の見積書をAI-OCRで電子データ化し、必要なデータをRPAにより会計システムに入力することが可能になります。
他にも、RPAツールにデータをデータベースに保存する業務を任せ、データ分析機能を持ったBI(Business Intelligence)にレポーティングやシミュレーションなどを任せるといった、BIとRPAの組み合わせも。
特に、紙をオフィスからなくし、手書きや印刷の紙データをデジタルデータに変換し、さらにデータ分析の対象とする一連の作業の流れには、AI‐OCR・RPA・BIツールを組み合わせた導入は必須と考えられます。
データ活用にもRPA・AIによる自動化は必須

例えば、データドリブン経営(収集したデータを分析し、その結果に基づいて経営戦略や方針を立てる経営手法)の会社では、膨大なデータの分析作業は自動化するべきでしょう。
その自動化も、AIとRPAの組み合わせが有効です。
RPAが高度な判断ができない・反復しかしないということは、判断を要する業務ではデメリットになってしまいます。しかし、判断に強いAIと組み合わせることで、それらのデメリットが小さくなり、自動化の効果は倍増するわけです。
まとめると、RPAとAIは同じ自動化ツールではあるものの、依拠する技術・適用できる業務が異なるため意味が違う、ということになります。
そして、RPAロボットとAI、この2つの機能を合わせ導入することで自動化・業務改善の効果が上がることもぜひ頭に置いておきましょう。
代表的なツールは?UiPath・WinActor・BizRobo!を比較

国内で最も使われているRPAツールがUiPath、WinActor、BizRobo!の3つになります。
UiPathは、米国のUiPath社のソフトウェアで、世界シェアでもNo1とされています。
WinActorはNTTデータ、BizRobo!はRPAテクノロジーズと、それぞれ国内ITベンダーの製品です。
すべてPC上動作するRPAツールですが、価格帯・サポート体制・強みに少しずつ違いがあります。
例えば、フローをレコーディングする機能に強いのがUiPath、大型運用を想定しているのがBizRobo!、小さく運用を始めるのに向いていて、検定・公式トレーニングが充実しているのがWinActorなど、それぞれに特色があります。
国内で紹介される導入成功事例や、活用事例もこの3つの製品に関するものが多い印象ですが、一方で自社の課題に合わせて、ツール開発を外注、または自社開発をする会社も増えています。
特に大型の運用を目指す会社には、自社開発あるいは委託開発でRPAソリューションを構築するケースが多いようです。
国内ではNECや富士通などが大型運用の委託開発に強い企業として知られています。
RPAツールとアウトソーシング・BPOの意味やコストを比較

RPAは自動で業務を進められることがポイントです。
これに対して、アウトソーシング・BPO(Business Process Outsourcing)は、その本質的な意味が業務委託であり、双方ともいわゆる「外注」です。
特にBPOは、コールセンター・ペイロールなどの社内の一部の業務を一括アウトソーシングすることを意味しています。
人の手に依存するか、そうでないかの違い
アウトソーシング・BPOは、人的作業が頼りであるという点で大きくRPAと異なります。
また、自動化の技術はアウトソーシング・BPOには必須のものではありません。
外注業者として、アウトソーシングやBPOをサービスとして提供するために、自動化ツールを使うことは契約の範囲のことであれば可能です。
アウトソーシングとBPOはその決定的なデメリットとして、人の手を使うこと、そしてその分人件費がかかることが挙げられます。
この点、RPAツールを使った自動化は、人の手に依存しない分、コスト・業務時間の両方がカットできることになります。
RPAには教育研修は不要
アウトソーシング・BPOのコストには、教育研修コストが含まれるのが一般的です。
専門知識や、高度な技術を必要とする業務の場合、多額の外注コストが必要になることもあります。
この点、RPAツールに教育研修は不要です。
コスト面だけでなく、稼働までの時間を削減することにもつながります。
RPA人材とは?エンジニアとの違い

RPA人材とは何か、という明確な定義があるわけではありません。
エンジニアではなくても、基本的なRPAの操作ができて業務に応用できる人であれば、RPA人材ということができるでしょう。
また、RPAベンダー各社が実施する検定に合格した方も、一定のスキルを習得したRPA人材ということができます。
RPA人材には、プログラミングスキルは必要ありませんが、プログラミング的な思考が求められます。
業務手順を細分化し、それをRPAシナリオとして組み立て、より効率的に自動化に導くことができればRPA人材といえるでしょう。
今後、RPAの拡大とともに、こうしたRPA人材の需要が高まっていくことが予想されます。
一方、RPAに関するトラブルシューティングやユーザーサポート業務、あるいはRPAツールを開発するエンジニアには、それぞれに専門的なスキルが求められます。
MICHIRU RPAは導入しやすい国産RPA、安心のサポート体制

MICHIRU RPAは、わかりやすいUIで初心者でも簡単に操作できる国産のRPAツールです。
ユーザー向けにオンライン勉強会も頻繁に開催されており、参加して基本操作をマスターすれば、初めての方でもすぐにシナリオを作成できるようになるでしょう。
また、プログラミングの専門知識は必要ないです。
そのため、社内のIT部門に大きな負担を掛けなくても、スムーズに導入することができます。
さらに、自動化できるまでレクチャーを受けられる親切なサポート体制もあります。
初期費用10万円、月額5万円で導入でき、ほかのRPAツールと比較して低価格なことも人気の理由です。
これらの特徴から、中小企業でも導入しやすいRPAといえるでしょう。
これからRPAを導入してみたいとお考えの方はMICHIRU RPAを候補に入れてみてはいかがでしょうか。
「関連用語の意味と違い」に関する記事のまとめ

RPAの基礎を学ぶために、基礎用語や、RPAの仕組みを知っておくことは重要です。
これからRPAを導入してみたいとお考えの方に向けて
- RPAとRDAのそれぞれの意味と違い
- FAとRPAのそれぞれの意味と違い
- RPAとAIそれぞれの意味と違い
- アウトソーシング・BPO・RPAの意味と違い
などを解説しました。
特に、それぞれの仕組みの違いやコスト面など、押さえておくと業務に役立つポイントです。
また、RPA導入後に後悔することのないよう、導入前に無料の説明会などを受講してから、比較検討することをおすすめします。