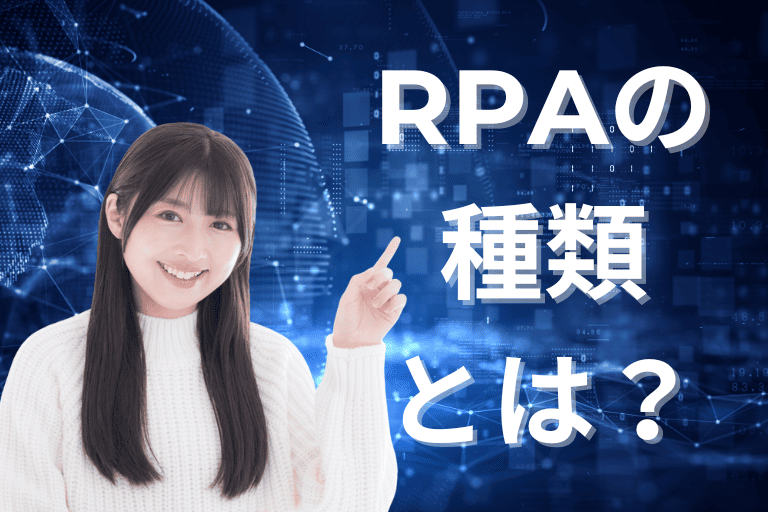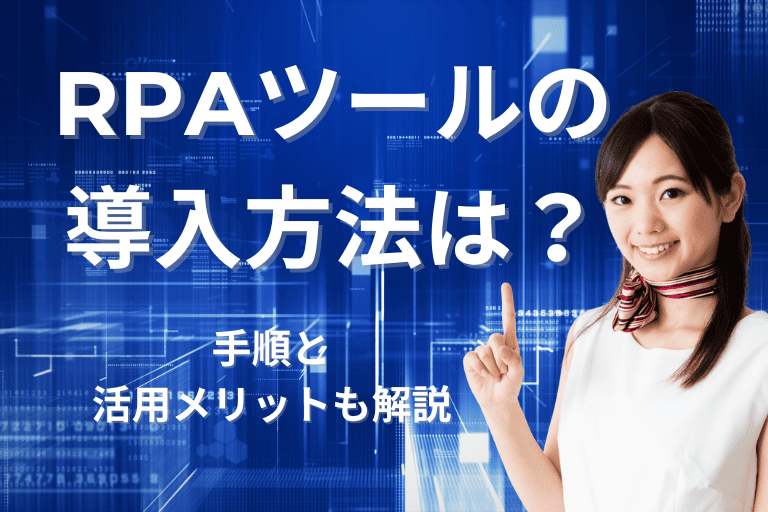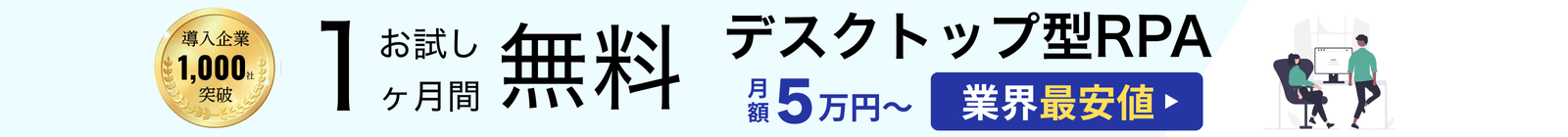「オフィスのロボット」とも言われるRPAツール。
業務を自動化し、業務時間を短縮し、生産性の向上やコストカットに非常に効果的であり導入企業は近年急増しています。
では、自社でRPAツールを導入するにあたってRPA担当者はどんな人が適任なのでしょうか?
実は、RPAツールにおいてプログラミングは基本的に不要であるため必ずしも担当者がエンジニアである必要はないのです。
そこで今回は企業に必要なRPA人材とはどういう人材か、そしてRPA人材の抜粋と育成の仕方について解説します。

株式会社MICHIRU 取締役 CTO
この記事の監修担当者:
斎藤 暁
医療施設法人やホンダ子会社のIT領域責任者などを経て独立。AI技術やシミュレータなど、複雑なアルゴリズムを駆使したシステムを提供している。自然言語処理によるシステムの技術は日米で特許を取得、その発明者でもある。2018年11月株式会社MICHIRUを創業。
RPA人材って、エンジニアだけですか?
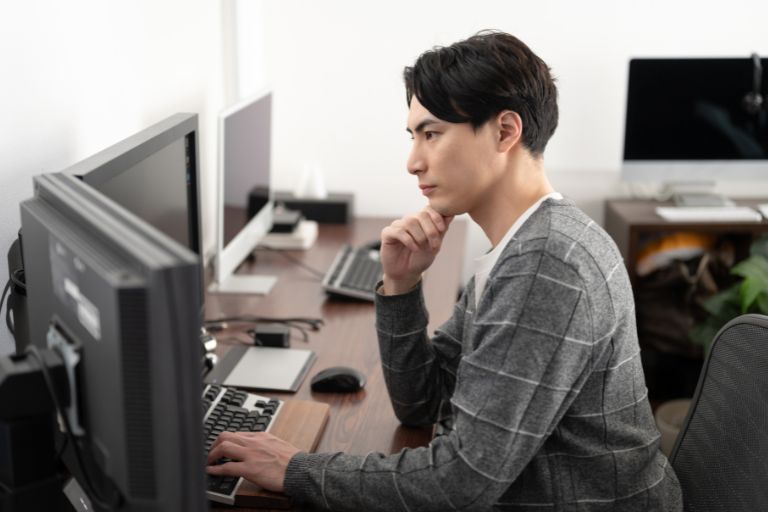
RPAによる自動化を行うためには、RPAツールを操作し、シナリオまたはワークフローと呼ばれる一連のロボットの動きを作ることが必要です。
「ロボット開発」と呼んでいるベンダーもありますが、行っていることはロボットそのものを作成することではなく、ロボットの動く筋道を作っているのです。
シナリオは非エンジニアでも作成することができる
このシナリオ作成作業も、プログラミングが不要で、エンジニアでないとできないものではありません。
例えば、WinActorや、UiPathのような代表的な製品も、また、近時多く登場している国内ベンダーの製品・クラウドRPAツールなども、エンジニアではない、業務担当者がシナリオを作成できます。
しかし、現在のところエンジニアも、非エンジニアも、シナリオを自由に書いてRPAを自在に動かすことができる人材は不足しているのが実情です。
RPAの管理も、エンジニアが行うとは限らない
RPAを多数動かすことになると、RPAの管理が必要になります。
RPAの稼働状況のモニタリングといったRPAそのものを管理ツールで見るのと同時に、業務の進行状況も管理するのが通常です。
今までの業務の管理者とは違う、業務管理のスキルが求められます。
しかし、これもエンジニアが行うより、プロジェクト管理スキルのある担当者が行うことを想定したほうが効率的て、現状にあっているという会社も多いことでしょう。
エンジニアが業務に精通するというより、非エンジニアでも使いやすいツールである限りは、業務の担当者がスキルを付けたほうが短い時間で対応できると考えられるからです。
RPA人材を確保する方法

RPA人材を確保する方法は主に下記の4つです。
それぞれ確認して自社に最適な方法を選択すると良いでしょう。
1.社内で抜擢して育成する
1つ目は、社内で適性のある社員から抜粋してRPA人材に育成する方法です。
社内でRPA人材を育成するメリットとしては、社内業務に詳しいので、RPAで自動化する業務の棚卸しや選定をスムーズに行うことができ、結果として効果を肥大できる傾向にあることです。
なお、ほとんどのRPAツールでは研修プログラム等が用意されていますので、社内にノウハウがない状態でも問題はありません。
さらに人材派遣会社・研修会社などでベンダー公式として認定されている研修・トレーニングも含め、多数のコースを提供しています。
あとで説明する通り、人材派遣業界でも、RPAのシナリオ作成スキルを登録スタッフに身に着けさせる動きが顕著ですので、十分な数の人員にスキルが身につくまでこのようなサービスを利用して人材育成することができるでしょう。
2..派遣社員を雇用する
2つ目に、派遣でRPA人材を雇う方法です。
派遣でRPA人材を確保する一番のメリットは、必要な人材を必要な期間だけ確保出来るという点です。
例えば大手派遣会社であるパーソルテンプスタッフは「RPAアソシエイツ」を派遣し、導入から運用の開始までをサポートするサービスも行っています。
定型的業務を行う人材が必要なくなるのではなく、派遣職員にはRPAを使った業務のスペシャリストとしての役割を担うことが業界全体で期待されています。
ただし、派遣で人材を確保する場合には、契約終了後の引継ぎ体制を整えておく必要があります。
3.キャリア採用する
3つ目に、キャリア採用を行いRPA経験者を新たに採用する方法です。
RPAツールは誰でも扱いやすいツールと言われていますが、使いこなせるようになるにはある程度の時間が必要ですし、担当業務も多く発生します。
大企業で大規模なRPA導入を行う場合などには、RPA経験者のノウハウや経験が必要不可欠になる場合もあるでしょう。
キャリア採用で経験者を確保したうえで、既存社員の育成を上手く組み合わせるなどしてもいいかもしれません。
4.アウトソーシングを活用
4つ目に、アウトソーシングを活用する方法です。
アウトソーシングのメリットは、導入の検討から開発・保守まで専門家が行うため、無駄のないスピーディなRPA導入と、初めてのRPA導入でもリスクを大幅に軽減出来ることです。
アウトソーシング先によっては、社内のRPA人材の育成プランを用意しているところも。
コストがかかってもRPA導入を確実に成功させたい!という場合におすすめです。
おすすめ!代表的オンライン研修

RPA研修は、オンライン研修形式で開催されているものが少なくありません。
会場での研修より、非常に数も多いので、仕事をしている人が空き時間を使って受講しやすいものが多いのです。無料講座も活用の価値があります。
主要なオンライン研修をご紹介しますので、社内研修プログラムに組み込んだりしてRPA人材の育成に役立ててみてください。
日本最大シェア製品を学ぶ・NTTデータ「公式」eラーニング 『WinActorオンライン研修』
WinActorの開発・販売元である、NTTデータが提供しているWinActorオンライン研修は、無料の初級講座から上級講座まで、オンライン研修を用意しています。
日本最大のシェア、WinActorを基礎から学び、導入に備える段階から、シナリオ開発・運用上のトラブルシューティング・管理の方法まで、1講座1万円前後~のお得な価格で学ぶことができます。
大きく分けてベーシックとアドバンスがあり、導入研修~技術者検定の中級レベル試験対策にも役立つ内容なので、受講者も目標設定がしやすい特徴があります。
人材育成に活用するための目標設定や学習のペース設定もしやすく、企業の研修プログラムにも組み込みやすい内容です。
無料で開発まで学べる「UiPath アカデミー」
UiPath アカデミーは、UiPath社が提供する無料のオンライン研修です。初学者~開発者・社内でUiPathの活用を推進する方に向け、どのレベルの方でも体系的に知識を深めることができる研修プロブラムです。
ベンダーが提供しているプログラムなので、内容には信頼性があり、UiPathのベンダー検定試験にも対応しています。
開発コースでは3-40時間とまとまった時間の受講が必要ですが、その他のコースは2時間ほど~10時間くらいまでで学べるコンパクトな内容のものが用意されているので、気軽に受講することが可能です。
基礎から使い方が丸わかり「blueprism オンボーディング」
blueprismもベンダーの提供する研修が充実しています。
blueprism Universityという体系的な研修プログラムへのフルアクセスは、英語版での提供ですが、日本語版のユーザー向け、しかも初心者からblueprismが学べる研修が「オンボーティング」です。
使い方の初歩から、開発につながる知識まで、コンパクトな内容でblueprismの知識を深め、仕事に閊えるレベルまでユーザーを引き上げます。
こちらもオンラインで研修を簡潔することができますので、社会人の受講には便利です。
初心者から開発・運用まで「ヒューマンリソシアWinActor 研修」
派遣会社などの人材紹介会社が人材育成のためにRPAの研修を提供しています。
中でも、ヒューマンリソシアの提供する研修は、WinActorの基礎から開発・運用など、ITプロ向けの研修までプログラムが充実しています。
有料のオンライン研修ですが、初歩~上級までのプログラムを一貫して学べる点や、研修テキストの充実ぶり、細かく区切りが見えて学習目標を立てやすいプログラム構成から研修の定番の1つとして活用されています。
人材育成も心配なし!初めての導入ならMICHIRU RPA

MICHIRU RPAは直感的に操作が可能で、非エンジニアでもシナリオを作成することができます。
サポートもきめ細かく、操作勉強会やセミナーなどRPA人材の育成サポートが充実しているのもMICHIRU RPAの強みです。
そして最大の魅力は、デスクトップ型RPAでありながら初期費用10万円、月額利用料金5万円という業界最安級のコストパフォーマンス。
低コストでRPA導入をスモールスタートしたい企業にはうってつけです。ご興味をお持ちの方はぜひ一度お問い合わせください。
記事まとめ
RPAの活用の幅を広げ、自動化を迅速に推進できるようには、対象業務を広げることと、多くの人員がシナリオの作成に当たれることです。
シナリオ作成や、部単位などのRPA管理などを行う人材を例えば部署ごとに育成しておくことは、RPA活用に有益と考えられますし、RPAに関するノウハウを蓄積することができます。
投資対効果も通常良好と考えられますので、御社に合った方法でRPA人材育成を推進してみてください。